以下の記事が自分にグサグサと刺さっている。
棚上げしながら書いてみるが、いつまでたっても精神が成長しない人って、どうしてもたまにいる。頭に何人浮かんだだろうか?
この記事では、その特徴が明確に言葉にされていて、悩みが氷解すると同時に、自分に当てはまる部分についてはぞっとしている。やはり僕も途上なのだ。
ーその中で一番僕がぞっとしているフレーズは何か?それは以下の特徴である。
完璧主義
・・・これのどこが悪いのか?みんな、パーフェクトを目指すじゃないの。
実はこれの裏には、記事を読んで初めて合点がいった深い深い闇が潜んでいる。今日はそれをテーマに色々書いてみようと思う。
『100点』が取れるとはどういうことか。
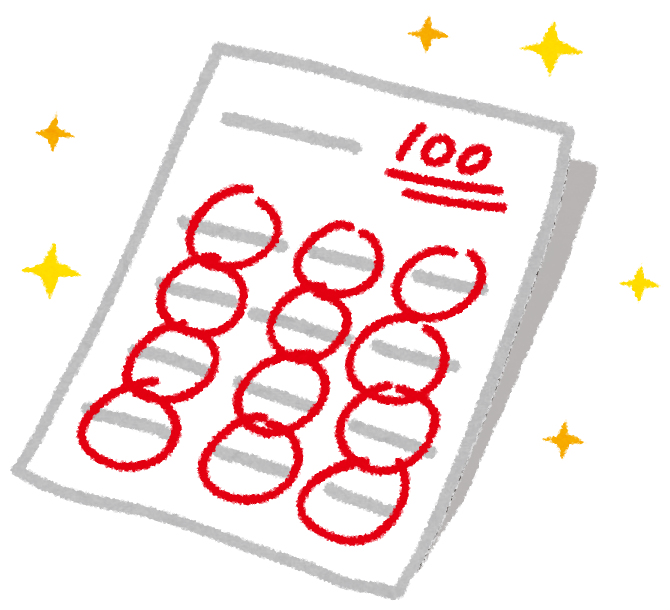
完璧主義により成長が滞る理由は、本当に『うぐっ!』となるので、あえて丸ごと引用してみる。
完璧主義と言われると、決して失敗をしない全てにおいて完璧な人をイメージするかもしれませんが、実際は、完璧主義というものは自分が完璧である状態を保つことができるような低いレベルに留まっているだけです。
自分が慣れ親しんだことやまず失敗することはないようなことに留まっているだけで、自分は完璧だと一生懸命思い込もうとしているわけです。
これはいわゆる老害予備軍で、自分が信じている常識の範囲内、自分が知っていることの範囲内、自分が失敗しない範囲だけで仕事をしたり物事の判断をします。
誰でも人は挑戦しなければ失敗はしません。
その失敗がなければ成長はありません。基本的に人間は失敗からしか学ぶことができません。
マジでこれは『うぐっ!』となる話である。つまり『100点が連発できる』とはどういう状況かというと、
とっくにそのステージはクリアしているのに、その外に出ず停滞しているだけ
ということなのだ。実際、小学校のテストで100点を取り続けても、全国レベルの模試だと大概コテンパンにされる。
それを恐れて自分が高得点を取れるステージに留まれば、確かに気分は良いだろう。だがそれ以外のメリットは多分ゼロだ。
仮にボロボロの点を取っても、そこからどうやってスコアを伸ばすか考えて、仮説を立てて、努力する。なるほど、そちらの方が健全だし、驚くほど差が付くだろう。
非常に簡単なテストで100点を取り続け、『あいつ50点やしww』と、難関テストに挑んだ奴を笑う。何というか、見ていて哀れになってしまう・・・・。
・・・てな感じでここまでさんざんこき下ろしてみたが、実はこの『100点の罠』とでもいうべき現象は、少しでも油断すれば僕らも簡単にハマる。
特に自己重要感が低い人はなおさらだ!
ここからはそれについての警鐘を鳴らしつつ、その打開策についての僕なりの方法を述べていく。
コンフォート・ゾーン。

心理学の言葉に、『コンフォート・ゾーン』というものがある。
『快適な居場所』という意味で、先ほどの例で言えば自分が100点を取れるであろう世界を指す。定義は本当に名前通りである。
人間は『同じ場所に留まることを好む』という性質があり、環境を変えることには本来多大なストレスを示すのが自然なことなのだ。
特にそれが、自分が勝ち続けられるような、比較的優位なポジションにいられる組織とかなら猶更だ。このことは別の何かに置き換えて考えるとわかりやすい。
まず、自分の居場所として非常に快適な最たる場所と言えば、『家』だろう。『home』という言葉に『拠点・拠り所』みたいな語源があるのを考えても納得。
そしてそこから少し離れれば、流石に家に居るときと同じ振る舞いは出来なくなる。とはいえ、極端な緊張にさらされることも無いエリアがある。
例えば『学校』『職場』から、広く言えば『日本』まではそう言って差し支えないだろう。これは『ストレッチゾーン』という。
さらにそこから飛び出れば、完全に未知で既存の知識がまるで通じないパニックゾーンになる。例えば『海外』とか、『まるで価値観の異なる世界』とか。
・・・こう考えれば、コンフォート(快適)な場所から、わざわざ不快な場所に出ていく方が不自然だと思われないだろうか。そしてこれは、肉体的ストレスに限らない。
地方の公立小学校では無双の天才と称された子も、都会の一貫校に入れば下から数えた方が速いケースなどザラだ。
自分のプライドがバキバキにへし折られる感覚。これはもう、完全にコンフォート・ゾーンから飛び出している。となれば、そのエリアに留まる方が自然な話だろう。
そしてこれは、外部からの刺激に対しても同様だ。この辺は僕がくどくど語るより、日本に存在する意味不明な既得権益の多さを読んだ方が自明である。
―これを考えれば、色々なことに挑戦する意欲が今あろうと、何かで結果を出してチヤホヤされようもんなら、そこから出ずに留まることは普通に起きるとわかる。
ではどうすればそれを防げるのか?何をしたらいわば『100点病』みたいな状況を抜け出せるのか?
こっからは、曲がりなりにも僕が取り組んでいる、ささやかだけど効果の高い努力について書いていく。
10勝5敗の大関であれ。
↑の本に書いてあった教えで大好きなのが、「10勝5敗」という考え方だ。ざっくり言えば、時には負けを作れないと、まだまだ未熟みたいな意味である。
『そんなもん全戦全勝じゃなきゃ意味ないゾー!』と思う方もいるかもしれない。
だが、実は勝ち続けるなんてのは本来異常であり、多分絶対安全なエリアでマウントを取っているだけというのは、先に書いた。
日頃からちょこちょこ失敗していれば、リスクを取ることにも鈍感になっていく。実はそういう基本的な話でもあると思えるわけで。
だから僕は、少しでもマンネリを感じたら、新しいことを試すってのをルーティンにしている。
例えば毎朝最弱のCPUと将棋を指して遊んでいるが、それの狙いは『新しいことに挑むことに慣れるため』ってのが大きい。(純粋に楽しいのもあるけど)
昨日は居飛車だったから、今日は思い切って中飛車にするか、とか。前回は守りに入ってみたから、今回は序盤から攻めに行こう、とか。2日連続同じ作戦は使わない。
もちろんたまに負けるが、結果『大したことないな』という経験値と、『じゃあ次はこうしてみるか』という仮説と、勉強しようという意欲が出てきて完全にペイできる。
他にも、今まで食べたことのないレトルトのカレーを選ぶとか、飲んだことのないコーヒーを優先して買うとか、細かいチャレンジは意識して取り入れている。
上手くいくこともあればいかないこともあるけれど、どちらにせよ「学び」を得られるし、それは『安全地帯にいること』よりも尊くて有益。
本当に細かい積み重ねだが、そう言うことがわかるため数年以上継続出来ている。無理にデカい一歩を踏み出す必要はない。まずは小さく踏み出してみてはどうだろう。
終わりに。
ってことで乱暴にまとめると、
『100点』ってすごく聞こえるけど、連発できているならそれは成長が完全に止まった証拠
ということになる。耳が痛すぎる。
どんだけ自己重要感が低い人でも、特技の1つくらいは持っているはずであり、その中でも意識して負けを作れているか?これって大切だな、と。
100点の罠はそこかしこで待ち構えている。頑張って避け続けたいと思う。
では今日はこの辺で。
