前書き
僕にできないこと。
そんなものは無数にあるのだが、その最たるものは「気にしないこと」だと考えている。昔から僕は、「気にしない」ことの技量が、全く上達していない。
人から攻撃的なことを言われ、落ち込む。所作に自分への不快感の表明を感じて、落ち込む。友達が多くないこと、背が高くないこと、彼女がいないことに落ち込む。
そんな風に負の感情に囚われていることを人に相談しても、「気にしなければいいんだよ」とだけ言われる。その度に、それはなんなのか教えてくれと、もどかしくなる。
社会において、コミュニケーションに伴う誤解や、謂れのない攻撃は、もはや前提となるエラーのはずだ。それらは減りこそすれ、決してゼロにはならない。
いわば、「気にしない」こととは、コミュニケーションを円滑に進めるために必要な、そういったエラーに対する精神的な受け身のようなものだと言える。
口調がきついのは、悪口ではない。会議での批判は、敵意ではない。一つ一つの経験から学び、時には口伝されながら、人は本来それを自然に会得するはずなのだ。
しかしその受け身が、僕は致命的に下手なのである。
何故か泳げない、何故かバットにボールが当たらない、そんな人がいるように、何故か僕には、気にしないことができない。
そんな風に、コミュニケーションにおける受け身が下手だとどうなるか。人の何倍も心にダメージを負い、辛い気持ちが強いままに持続し、生きてて楽しくなくなるのだ。
―先日、とあるクレーム案件の電話を受けた。相手は相当慣れているようで、こちらを追い詰めるような発言や間を、狙って何度もぶつけてきた。
言外に込められた僕への攻撃。そんな不条理なことなど、それこそ気にしなければいいのだが、それができない以上、全てが自分への評価として刺さる。
その人にとって僕は、社会不適合だし、格下だし、話が通じないし、愚かだし、怒られて当然な、ゴミ以下の存在なのだ。
ここまでボコボコに言われると、なんというか、苦笑しか出ない。自分が絶対的に優位で徹底的に正義だと、どうしてそこまで確信した物言いができるのか、不思議だった。
ただ僕は、いい加減理不尽に対し、「そんなことを考えるのはなぜなんだ・・」と考えるのを止めたい。
理不尽は、「そういうもんだ」というあしらいで、もう終わりにしたい。
でなければ、いずれ僕は、僕を完全に否定してしまう。このロジックでいくと、「つまり僕のせい」というところに、必ず収れんするからだ。
だからこそ、「気にしない」とはなにかを学び、習得したいと、改めて心に誓っている。アホに消費される自分を放置するとか、クソみたいな人生じゃないか。
もう一度ゆっくり、自分に問いかける。「気にしない」とは、なにか。今からその答えを、真剣に探そうではないか、と。
この記事は、自分が納得できる場所に辿り着くまで公開しないと決めてから、書き始めている。それこそ、ビジネス書の一章分を書くつもりで、かなり推敲を重ねた。
ここに書いたことが、皆様の役に立つかどうかはわからない。あくまで、僕は僕を救うため、この記事を書いている。
ただ、「気にしない」ことに悩む人に対して、少なくともヒントになることは書けていると、そういう自負はある。だから暇なときにつらつらと、読んでみてほしい。
ということで過去最大文量の記事、なるべく目次はたくさん用意したので、好きな箇所からぜひどうぞ。
- 「気にしない」ことの解像度を上げる。
- 「気にする」とはなにか。
- 感情を支配する。
- 「嫌われる」恐怖を克服せよ。
- 「スルースキル」は”無視する力”なのか。
- 終わりに:僕にとって、「気にしない」とはなにか。
「気にしない」ことの解像度を上げる。
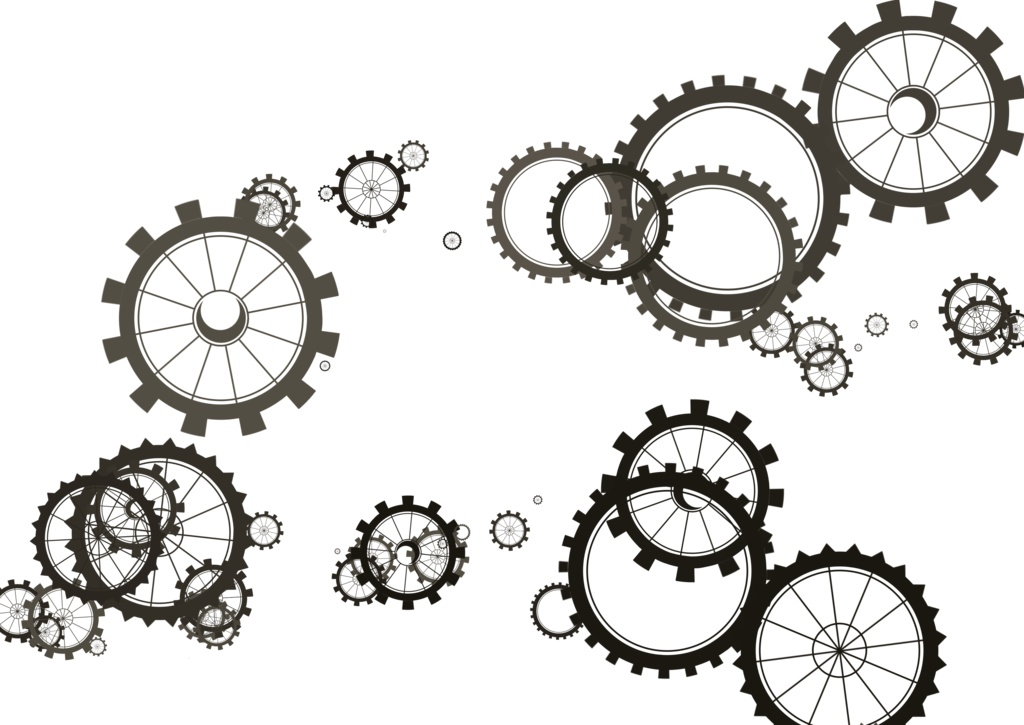
先述の電話のあと、過去例を見ないほどの胃痛を覚え、同時に大きな空虚感に襲われた。それは、激しい怒りや屈辱という感じではなかった。
もっと丁寧に考えれば、「納得できない」「胸糞の悪さ」と形容した方が正確だ。これらは両方、怒りというより不快感の方が、表現として近い。
まずはここから始めてみよう。この2つの言葉を、昔の人たちはどう定義し、表現したか。辞書にはこう書いてある。
胸がむかむかするほどである。いまいましい。「考えただけでも―・い」
新しく「忌ま忌ましい」という、また違う感情を表す言葉が出てきた。だからこれも、辞書で引いてみる。
1 に腹立たしく感じる。しゃくにさわる。「―・い泥棒猫め」「―・いことに今日だけ天気が悪いらしい」
2 けがれを避けて慎むべきである。すべきである。
「ゆゆしき事を近う聞き侍れば、心の乱れ侍る程も―・しうて」〈・蜻蛉〉
3 である。が悪い。
「かく―・しき身のそひ奉らむも、いと人聞き憂かるべし」〈・〉
この定義を読んでいくと、忌ま忌ましさとは、「不快と怒りの混合感情」の様に読める。つまりは、非常に強い憤りなのだ。
僕は強く苛立っている。同時に不快感も覚えている。そう捉え直して自分の胸の内を観察すると、なるほど、確かにその通りだと納得ができる。そこは認めよう。
ところで苛立ちとは、自分の期待を他人が満たしてくれないときに抱く感情だと言われる。では、僕は正直めんどくさいだけの人に、何を期待して、苛立っているのか。
その疑問を紐解くカギは、義務教育下で何度も教えられる「性善説」にありそうだと気づいた。
ということでここからは、この「性善説」について調べてまとめた、”身も蓋もないこと”を書いていく。
「話せばわかる」なんて大うそ!
「話せばわかる」という考え方は、疑うことすらタブーのような、高尚な常識という風に聞こえる。
この言葉にも表されている通り、誰しも必ず最後は理解し合える、道徳的に素晴らしい人になることができる、そう信じる立場が「性善説」だと思う。
ただ、その考え方は、いささか無邪気過ぎるのではないか。むしろ、わかってもらえないのは自分のせいという思考に繋がりやすいため、危険な点もあるのではないか。
SNS上でのやり取りを見ていても思うが、話せば必ずわかってくれるというのはある意味非現実的な理想だし、言ってしまえばただの妄想でもある。
現実はもっとシビアであり、どうしようもない場面や人は、必ず登場する。
そういう風土や人と相互理解し、打ち解けることは、非現実的なのだと、僕は今こそ理解すべきなのではないか。
そんな葛藤もあって、僕にとっては「性善説」よりも、クレーマーに関するとある弁護士の言葉の方が、とても救われる心持がした。
それを丸ごと引用する。
基本的にクレーマーは、説明を聞いて自分が納得するということを想定していない。いつまでも顧客であることをかさに質問攻めにする傾向がある。
会社としては、丁寧に説明すればわかってくれると性善説で立ち向かうもたいていの場合には失敗する。そして時間ばかりが経過することになる。
(中略)
「ここまで説明したら納得する」という明確な基準はない。相手として納得する気がなければ、どれほど説明をしても「納得できない」と簡単にあしらわられて終わってしまう。
まじめで優しい人にこそ言いたい。人間できることとできないことがある。どれほど丁寧に対応しても相手に理解してもらえないこともある。
まじめで優しい人ほど「わかってもらえないのは自分の説明がうまくないからだ」と誤解して悪循環に陥ってしまう。それは違う。
話を聞くにしても常識というものがある。丁寧に話を聞くにしても言われるがままに受け入れるのは意味が違う。話を聞くにしても常識の範囲がある。
何度説明をしてもわかってもらえないならあきらめるのもひとつだ。
よく「あきらめたらいけない」と言われるが時と場合にある。あきらめないと自分自身を追い詰めることにもなりかねない。
相互理解する”気が無い”相手を信じ抜く。なんとアホだろうか。血縁があるわけでもないのに、無条件で信じてあげる理由は、どこにも無い。
実際、「どんな人も最後はわかってくれるさ!」という風に結ぶアドバイスは、ほぼ見当たらなかった。
なんなら、この世は全て陰と陽。影があれば光があり、ヤバい人がいるからまともな人もいる。それが真理であり、全員が善人なんてのは身勝手な妄想に過ぎない。
そう説くブログもあるくらいだ。過激な思想に聞こえるが、不思議と反発する気持ちはなく、むしろ「やっぱりそうか」という、安堵とスッキリが混ざった感覚がある。
―やはり、「性善説」は、単なる義務教育下の洗脳に過ぎないのかもしれない。嫌いな食べ物は避ければいいのと同じで、面倒な人のことも(可能な限り)避ければいい。
つまり、まともじゃない人もいるという、至極当たり前の考え方にシフトすること。もっと言えば、「性善説」を自分の中で捨てること。
それが僕における、「気にしない」を会得するための、一つの始まりとなりそうだ。実際、ストレスのほとんどは、その根っこが「性善説」と密接にリンクしている。
例えば、「人を嫌いになってはいけない」「人から嫌われてはいけない」という「性善説」がため、理不尽を御せずに苛立ってしまうのではないか。
そう捉えると、やはり僕においては、「性善説」が負のドミノの1枚目になっている。そこを取り除かない限り、僕は永遠に、負の感情をどこかに秘めることとなる。
それについてもっと具体的なアドバイスが欲しい。あるいは、せめてヒントは無いものか。だからさらに、ここから考察を深めていくことにしよう。
「気にする」とはなにか。

ただここで一旦、逆の問いを入れてみたい。それは、「気にする」とはなにか、というものだ。よく考えれば、「気にする」という言葉も、抽象的でつかみどころがない。
そこで、「気にする」という言葉について辞書を引くと、こう説明されている。
心にとめてに思う。する。「人がなんと言おうと―◦するな」
端的で非常に分かりやすいし、至極その通りだと強く思う。心にとめて不安に思うという話などまさに「気にする」という動詞が示す動作そのものだろう。
心理学の文脈でよく出てくる「反芻思考」もまた、つまり「気にする」の極地だと思えてくる。気にすることが何度も繰り返すことを、反芻と表現しているのだ。
―ところでこの「気にする」というネガティブな響きの言葉について調べていく内に、非常に興味深く、何なら衝撃を受けたレポートに行き当たった。
それは元々、教育場面における理不尽な経験を集め、それらがどのような心理的影響を人に与えるのかを検討するための調査だという。
またそれに加え、理不尽な経験を割り切れる人がいる一方、状況を変えるために行動を取る人もいることについて、批判的思考と関連させつつ検討することが狙いだそうだ。
その結果の中で特に興味深かったのは、この部分だ。
中山ら(2022)[2]が大学生212名を対象に調査を行いました。
その中で「論理の重視」と「緊張・不安」「抑うつ」「疲労」「混乱」の関係性を調べた結果、すべて正の相関だったことがわかりました。
これを読んで、僕の中で「気にする」という言葉の意味合いが、ガラッと変わってしまった。「気にする」とは、論理的に考えることと、ほぼ同義なのか、と。
僕は、感情ではなく論理的に考えることが己の個性であり、そして自分にとっての武器なのだと、自然と前向きに捉えていた。
しかしそれも表裏一体で、少し間違えれば「考えすぎ」に至る。そのレポートは、そのことを仄めかしていた。そしてそれは、確かにその通りだと思う。
論理的思考が行き過ぎると、「なんで、どうして」という反芻思考に容易く変化し、気付けば始まりと終わりが繋がった自責のループに乗ってしまう。
そしてその根本的な原因が、因果をどこまでも考えてしまう様な思考そのものにあるとしたら、なかなかに痺れる答えではないか。
あたかも、八方塞がりに陥ったような気持ちになる。自分の思考の癖そのものが、「気にする」ことそのものであるなら、つまり僕はどうしたらいいんだ、と。
だからここからは、「思考」と「気にすること」の折り合いをつける方法について、更に調べていくことにしよう。
病んだ気を解毒せよ。

それに関するヒントは、幸いなことにすぐ見つかった。
思考や論理、感情について、僕に新たなヒントをくれたのは、やはり仏教であった。その宗派の1つ、テーラワーダ仏教の、アルボムッレ・スマナサーラ長老の言葉。
それを読むことで、僕の中で目から鱗が落ちる感覚を得られたのだ。対談記事の一部だが、引用して紹介しよう。
小倉:例えば、瞑想とかで「無になる」と言いますよね。修行の世界ではそういうことも学んでいくんですか。
スマナサーラ:瞑想を始めた瞬間に、我々は無になることを教えるんです。こんなことをしたら無になりますよと。「無」というか「空(くう)」というんですね。
なってから観察して下さいと。
小倉:簡単になれますか。
スマナサーラ:すごい簡単です。
小倉:僕、「目をつぶって瞑想しなさい。無になりなさい」って言われても、いろんなことが頭に浮かんできて、なかなかできないと思うんですよ、僕の性格から言うと。
スマナサーラ:伝統的に思われている瞑想は、”仏教の瞑想”じゃないんです。”仏教の瞑想”は、“observation=観察”なんです。観察する時は、思考が邪魔なんです。
小倉:観察する時は、思考が邪魔。
スマナサーラ:だから思考をやめて、観察する。
・・・これを読んでどこにハッとしたのかというと、それは思考と観察は別物だという指摘そのものにある。
僕は観察というのは、対象をずっと見つめ、常にそれに対し疑問や仮説を投げかけ続けるような行為だと思っていた。
しかしそうではなく、いわば思考すら邪魔だと解釈し、ただそのものを眺めることこそ、観察なのだ。そういう考え方もあるのだと。
観察と称した思考が、大体自責とか不甲斐なさに行きついてしまう僕にとっては、その解釈の方が凄く腹落ちする。
そして長老は、思考という頭の中で起きていることについても、僕にとっては新鮮な切り口を語っていた。
一般的に思考とは、考えることです。思考とは、言葉で考えることだけではありません。概念の回転も思考です。
概念には言葉は要りません。言葉がなくても私たちが知っていることはたくさんあります。それから、感情の回転も思考とします。
思考とは、心の仕事のこと全般をいうのです。
心の仕事全般を、ひっくるめて思考と呼ぶ。言語化できたものを材料にグルグルと思い巡らせていくことをそうだと考えていた僕にとっては、やはり意外な解釈であった。
さらに長老は別のインタビューで、悪感情の”解毒薬”についても語っていた。尚、ここでいう悪感情とは、不快感や罪悪感、苛立ちなど、その辺の総称のことを指す。
また、しつこい悪感情に対しては、特に慈(慈しみ、友情)・悲(他の生命を助けたいという気持ち)・喜(他人の幸福を自分のことのごとく喜ぶ気持ち)・捨(一切の生命を平等に受け入れる気持ち)が解毒剤になります。
慈悲喜捨という善感情を育て、心を成長させ、その善感情でもって悪感情を解毒するのです。
慈・悲・喜・捨。これらの深さと及ぶ範囲には限界が無いため、別名「四無量心」とも呼ぶそうだ。そしてこれこそが、心に巣食う毒のような感情を解毒する、と。
ここまでの話をまとめると、負の感情を"気にしているとき"に僕が取り組むべきことが、明確に見えてきた。
まず悪感情に囚われているときは、その思考を意識的に止めて、観察に入る。そのうえで、四無量心という解毒剤を、自分に注いでやる。
なるほど、すごく合点のいくプロセスだ。もっとも、「わかる」と「できる」は別物だと言われるので、ここから僕には、具体的な練習が必要なんだけど。
ただそれはそれとして、ここでは一旦棚上げする。まだ飲み込み切れない部分が、一つ残されているからだ。
それは「捨」だ。慈・悲・喜の3つが言わんとすることは何とか追えるのだが、「捨」だけがどうにも、ピンとこない。
まずそもそも、”何を捨てる”のだろうか。それにそもそも、なぜ捨てることが、悪感情の解毒になるのだろうか。捨てることが苦しみになる人もいそうなのに。
そう思って調べていくと、実は「捨」には意味が2つあるとわかった。つまり、僕らが考える、「何かを捨てる」という意味”だけじゃない”のだ。
順番に紹介してみよう。まずはこちらの説明から。
もう一つは「無関心」「中立、平等」ということである。漢字の「捨」の語義に照らせば、「顧みない」「捨て置く」ということになるであろう。
この場合、「捨」は心のあり方、心の作用を示したもので、「心が特定の対象に向かわず無関心」「心が対象に関して中立、平等」ということである。
しかし、心が対象をまったく無視したり無関心で働かないということではなく、特定の人やものに執われずに平等であることである。
続けて、もう1つ、同じく「捨」に関する話を紹介する。
「心の平静、心が平等でざわつかぬこと。心を暗く沈んだ状態や、病的に昂奮した状態から離れさせ、平等な平安な状態にする作用。かたよらぬこと、人に対して平等であること」
などの意味が説かれています。
この中で「心を暗く沈んだ状態や、病的に昂奮した状態から離れさせ、平等な平安な状態にする作用」が四無量心の「捨」として説かれます。
こう考えてくると、「思考を止める」というアドバイスが伝えたいことも、段々理解できてくる。
すなわち、慈悲喜捨で言えば、捨が最初なのではないか。自分が過度に、特定の対象に対し、思考や感情を向けていることを自覚し、そこから距離を置く。
例えば周りの環境に意識を割り振ってみるのも、広義の「捨」だろう。室内の音、コーヒーの香り、味、等々。
それを経て、執着した思考を捨てたら、しっかりと自分を観察し、落ち着いてからゆっくりとケアすればいい。すごくシンプルだし、拍子抜けするほどに簡明だ。
正しく”気にする”ことに、思考は要らない。僕のアイデンティティを揺るがしそうな考え方ではあるが、だが同時に、自分に必要な観点の様にも感じている。
感情を支配する。

思考には感情も含まれるとスマナサーラ長老は語っていたが、こちらの方が圧倒的に知覚が困難だ。
自分がどんなことを考えているかはきちんと言葉にできることが多いが、自分がどんな気持ちなのかを述べるのは、格段に難しい。やってみると解ると思う。
しかしその「感情」をきちんと認知し、不必要に増大させないようにしないと、真の観察はおろか、心の平穏さえ夢のまた夢にまで遠ざかっていく。
ここで思い出されるのが、斎藤一人さんの言葉だ。出典を忘れたので雰囲気しか書けないのだが、こんな発言が残っている。
辛いときに辛いと思うのは当たり前。そんなときでも、どうやって自分の機嫌を取るか。どうやって楽しいことを考えるか。それが大事なんだよ。
辛い反応に辛いと返すのは簡単であり、そこを如何に止めるか、あるいはユーモアに転換するか、それこそが修行。こんな風に話が続いた気がする。
これはまさに、感情に振り回されないことであろう。そして同時に、僕にとって「気にしない」ことと同じか、それ以上に苦手かもしれないことでもある。
僕は簡単に、自分の感情に振り回される。それは認識している。
だから自分に問う。では、”振り回されないとは何か”、と。そのとき、すごくヒントになったのは、この教えだ。
当てにならない感情よりもどう生きたらいいか。今一瞬を生きるためには、私は目的本位の生き方にするのが大事だと思ってるんです。
感情はどうでもいいんです。放置してください。何か過去の悩みとか未来への不安を抱えたままでいいんです。
それをどうにかしようと思わずに、その不安なまま、煩ったまま、手を動かし、足を動かしてみてください。やるべきことは必ず目の前に何かしらあります。
洗濯を畳むとか掃除機をかけるとかなんでもいいんです。何か手を動かし、足を動かしているときに感情から離れられる。
そして、そのときに今一瞬を生きるという生き方が見えてくると思っております。お釈迦様が説かれたことは感情本位から目的本位に生きる。
その生き方だと思っております。
感情を放置し、行動に集中する。感情は「変えなければならない」と思っていただけに、「本当にそれでいいのか?」と、どこか無責任ささえ、感じてしまう。
しかし同時に、この考え方は面白い。そして深い。直感でそう思った。だから改めて、この言葉を読み返す。
目的本位。「本意」ではなく、「本位」。調べてみると、「判断や行動の基本や軸なるもの」という意味であった。
感情は僕に、落ち込め、苦しめという思考を強いる。それに従えば、当然心は毒に中てられていく。
だが目的を本位にすると、それを叶えたいなら感情は二の次で、とっとと行動しなければならないということが、ひしひしと伝わってくる。
そして目的に向かって行動を始めるとき、感情はなりを潜める。感情を無視することが、感情の制御に繋がるかもしれないというアイデア。
すごく納得だ。感情に従ってクヨクヨするか、目的を重視して行動するか。答えは当然、後者なのだ。
感情を制御する方法として、これほど単純かつ明快で、効果がある考え方はなかなか無いのでは、と思わされる。
「嫌われる」恐怖を克服せよ。

「気にしない」という心境を阻む難敵は、まだ潜んでいる。それは他者に対する過剰な忖度、ひいては「嫌われる」恐怖である。
僕自身、頭の中では別に嫌われることについて、そこまで恐怖心めいたものはない。むしろ今恐れているとすれば、それは、積極的に嫌われる一手を打つ場面だと言える。
現在僕は、具体的には少しぼかすが、長年通ってくださっている顧客の一人に、「態度の改善が見られなければ止めてもらう」と告げねばならない場面にいる。
これは感情的ではなく論理的に出した結論であり、今手を打たなければ、携わる他のスタッフ、ひいては組織の疲弊に繋がる。遠慮なく言えばがん細胞なのだ。
しかしこの決断によって、どんな未来を引き寄せるのか。それが見えずに僕は怖気づいているのを認めている。
例えば、逆恨みされてネガティブな口コミを積極的に流される、粘着されてアンチ活動をされる、その辺が浮かぶ。ただ、円満な離別という未来だって引けるはずだ。
だからこそ、二つを並べると合理的判断はどちらなのか、考えるまでもないように思えてくる。
今のままでは組織が崩壊するという最悪のシナリオが確実に待っている選択肢と、悪い未来を引く”かもしれない”という選択肢。
情を抜きにすれば後者をとっとと選択して、それを前提とした作戦を考えることに頭を使うべきだ。そんなことはわかっているのだが・・。
感情という原始的な部分が、「いや、でも」というブレーキを、僕に踏ませてくる。この二つの手のどちらも避けつつ、落としどころは探れないものか、と。
僕はリーダーとしてあまりにも弱腰だ。最後の一押し、そこを踏み抜く勇気はどこから出てくるのか。エイヤッ!という気合なのだと皆は言う。
では、僕にとってもそれが最適解なのか?どれだけ「勇気出せ!」と頭の中で反響させても、最後の一歩は相変わらず重く、心臓の動きが鈍くなった感覚が強まる。
そんなとき、僕にとって大きなヒントになったもの。それは珍しくも仏教ではなく、認知行動療法的な考え方、もといバイアスだ。
今の僕の理性を歪めているバイアスは何か。それの正体が分かれば、僕はもうちょっとくらい、感情という暴走しがちな乗り物をうまく操縦できる気がする。
僕にとっての中立のイメージ。それは、虫かごや水槽の中の生物をただ眺めるように、僕と僕のバイアスをひたすらに観察することである。
距離を取るために、一つ一つの歪みを認知し、そこにラベリングをして名前を与えていく。
これは確かに僕の感情の一部ではあるが、既に固有の名が与えられ、数多の人たちが観察してきた、普遍的かつ一般的な認知の歪みなのだ、と。そう納得するために。
バイアスを知るためには客観視が必要である。これ自体がなかなか抽象的なのだが、このことを理解する、とてもわかり易い例がある。
それは、自分の顔にソースが付いてることを自覚するためには、鏡を通して自分を見なければならないというものだ。
主観的である限り、僕らは自己に起きているある種のエラーを感知することさえできやしない。本当にそう思える。
ということでここでは、数多の種類が存在するバイアスの内、特に僕にとって頻繁に発動するものを紹介する。
今の自分は本心ゆえの感情なのか、それともバイアスによって歪められたそれなのか、その理解の一助にするためだ。参考になれば嬉しく思う。
【敵意帰属バイアス】により、世界は敵だらけになる。
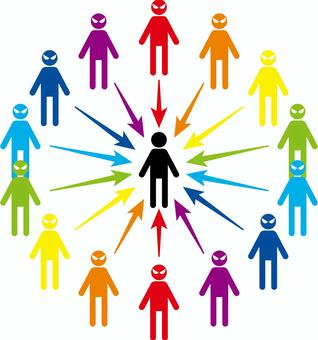
この言葉を知ったのは、西野亮廣氏のブログに書かれたやり取りだと記憶している。
このバイアスを簡単に言えば、他者からのコメントや態度に、本来存在しない敵意を感じ取ってしまう、というものだ。
例えば自分が出した意見に対し、「それってこうした方が良いんじゃない?」と他人から言われた際、「俺のことが嫌いなんすか?」と本気で返す人がいる。
あるいは、Xでのやり取りもわかり易い。VIP席の設計が大事だと書いた人に、「貧乏人は来るなってことか!」と噛みつくヤバい人も、最たる具体例の1つである。
こんな風に、敵意を勝手に作り出し、自分に帰属させ、それに振り回されてしまうことを敵意帰属バイアスと呼ぶ。
想像に難くないが、このバイアスに囚われた人とは、論理的な議論のやり取りは望めない。対案は反対意見であり、異論は非難なのだから。
そして僕は、この敵意帰属バイアスが時たま自分に発動しているのを感じて、慄然とすることが、今だにある。
会議での自分の発言に対するコメントによって心に小波が立ったとき、僕は健全な状態に無いことを、こっそりと自覚し、そして反省している。
このバイアスに呑まれている限り、世界は全て自分の敵になってしまう。”自分以外の全てアンチ”にその人を変えてしまうのが、敵意帰属バイアスの最たる恐怖だ。
尚、このバイアスの原因は、自己肯定感・自己重要感の欠如が大きいという。自分を認められないからこそ、敵意を振り乱し、自分を守ろうとするのだ。
そんな風にダイレクトに指摘されれば、ただただがっくりするしかないのだが、自分を他人のように大事に思うことも「気にしない」ためにはマスト。
自分が大切だと思えるようになれば、世界から敵が消えるという日々を目標に、このバイアスへ少しずつ立ち向かっていければと考えている。
【ネガティビティバイアス】と【投影バイアス】により、自分の全生涯に黒い光が差す。

漫画と小説を合わせて「こころ」は何周も読んだが、特に心に残っているフレーズは、先生の遺書のこの部分だ。
「もう取り返しが付かないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯を物凄く照らしました。」
軽々しく使いたくない言葉だが、僕はこれの言わんとすることが、すごく”わかる”。
仕事で失敗したとき、大事な人が去っていったとき、生徒が心の病気で苦しんでいると知ったとき、僕は僕の全生涯が黒い光で照らされるような心持になる。
自分が考えてきたこと、実行したこと、力不足であること、その全てが起因となり誰かの人生に影を落とした気持ちになり、故に自分が社会の罪人とさえ思えてくる。
今も実は僕の裁量で通塾をお断りしたご家庭からのメッセージを読みながら、胸の内につっかえたものと居た堪れなさを覚えており、つまり、辛い。
そしてこの辛さは未来永劫続くような気がしている。少なくとも、終わりは見えていない。残りの一生がとても黒くて暗いものになろうとも、納得しそうな自分が居る。
―この異常ともいえる心境を説明するのが、【ネガティビティバイアス】と【投影バイアス】の2つだ。きっと僕は、この2つが同時に発動し、強い苦しみを覚えている。
基本的に全ての物事を、僕はネガティブに考える。それ自体は行動と準備を促す一助なので、良い風に活用できれば、別に問題は無い気質である。
厄介なのは後者の【投影バイアス】だ。ネガティビティバイアスが、現在を黒く塗りつぶす思考であるなら、投影バイアスは、過去と未来を黒くするような認識である。
例えばオセロの白が黒にひっくり返るように、「10年前のあのときに状況がそっくりだ・・俺の不幸はあの時に始まっていたのか」という負の解釈を過去に与える。
あるいは、「こんなカルマを背負ったんだから、ロクな未来も無ければ死に方もしないだろうな」という諦めを未来に見出す。ただの厨二病なのだが、バイアスは強い。
では、この厄介なバイアスを打ち破るのには、何が必要なのか。それは、データと行動だ。行動本位に無理矢理でも思考を切り替えて、とにかくまずは動く。
その上で自分は悲観的な目線になっていると自覚し、現実的にその可能性はどれくらいなのか、可能ならデータに当たる。そして、目を覚ます。
日本人は元来ネガティブな人が多いとされるからこそ、これはバイアスではなく文化という考え方もできる。しかし要はやはり、使い方と解釈だ。
僕の未来は別に黒くない。そして別に、輝いてもいない。未来はまだない。そして過去はただの妄想だ。だから今現在以外、見る必要はそこまで無いのである。
そう思うと、心がふっと中立に戻るのを感じる。この心境は無責任でもなんでもなく、「ではどうするか」をドライに考えるための、最初の一歩なのだ。
バイアスは本能における認知のバグなので、意識で矯正するのは極めて難しい。だから、抑え込むのではなく、乗りこなし、制御することの方が大切なのだ。
そう思えば、僕の頭の中には最初から、多種多様な秘書が常駐しているようなものである。インサイドヘッドではないが、そう考えると可笑しくもある。
「スルースキル」は”無視する力”なのか。

この記事を書くために色々調べたり考えたりする中で、僕は「スルースキル」について少し思い違いをしていることに気が付いた。
「スルースキル」とは、僕は相手の存在や言動、感情という本能が感知するあれこれを、意識的に”無視すること”がそうなのだと考えていた。
だが本当のところは、スルースキルとは、相手を無視することを目的としたスキルではないらしい。実際、そのゴールは、意識的に無関心となることであるとされる。
あるいは、マイナスの出来事を「ただの出来事」という解釈に意識的に変えること。これこそがスルースキルの本質なのだと、色んな例を読むにつけ、悟りつつある。
このことを知ったのは、以下の記事を読んだことがきっかけだ。
特に以下のこの部分を読んで、「観察力の鍛え方」で知ったバイアスの話も登場したことから、すごく腑に落ちた感覚を抱いている。
スルースキルを高めるための第一歩として出来事をまずは他人事として理解することから始めると良い。
自分のこととして捉えてしまうと、必ず自己否定あるいは自分肯定バイアスがかかる。
そうなってしまうとかなりの確率で行動の判断ミスを起こしてしまう。
先ほどの例で言うと、自分視点で考えすぎてしまうことで自己肯定バイアスからミスを認めたくない心理が働き、言い訳をしてしまうなどである。
(友人に仕事で失敗した話をされて、言い訳をすることを推奨はしないだろう。)
出来事を他人事として受け止める。スルースキルの本質がこちらなのだとしたら、一般論的な「そもそも相手にしない、受け止めない」という解釈にズレを感じる。
そして僕は、前者こそが目指すべきあり方で、かつ心身にとって健全であり、そして僕が到達したいスルーの極地であるように思う。
人間は自己否定に、性質として弱い。そこは鍛えてどうこうなる問題ではない。どれだけ筋骨隆々になろうが、炎や電気そのものには耐性を持てないのと似ている。
だから自己否定的な思考を食い止めて、ミスといった出来事を全て他人事として受け止める。これは無責任ではない。むしろ適切な判断を下すために必要な思考である。
スルースキルとは、無視ではなく、無関心さを意識的に己の内に呼び覚ますスキル。「どうでもいい」という感想や解釈こそが目的地というのも、すごく面白い話だ。
だから引き続き、この辺りの解像度を上げていこう。「無視」と「無関心」は、どう違うのか。続いては、これを掘り下げていく。
「無視」と「無関心」の違いはなにか?

さっきも書いたが、無視と無関心は、何がどう違うのだろう。似ているからこそ、何がそれらを分かつのか、まずはそこを僕は知りたい。
まず無視とは、その対象を「見ない!」と決めることだ。しかしそれはつまり、心の奥底ではそれに対して、意識が向いている状態ではないだろうか。
例えばクモが苦手な人にとっては、たとえ視線を外して壁に張りつくそれを無視しようが、そこにいることには変わりない。その存在に、意識のほとんどを食われている。
一方無関心とは、心底どうでもいいという状態であり、その相手について徹底的に興味が無い状態と言える。
先程のクモの例で言えば、それがどうでもいい人にとっては、壁にでかいアシダカグモが張り付いていることすら死ぬほどどうでもいいので、何の感想も持たない。
こう考えてみれば、やはり目指したいのは後者であり、無視は良くてその過程、あるいはそもそも全く別方向の考え方であるともいえる。
見ないことと、思わないこと。文字にすればほとんど違いがなさそうだが、これらの間には、分厚い壁が何重とあるかのような遠さを感じている。
「無関心」をどう使いこなすか。

では、話を更に進めよう。無関心さを狙って再現するとだけ言うと、どこか矛盾した響きを感じる。
ポケモンみたいに、1,2のぽかんで意識を飛ばすわけにはいかない。どうすればいいかを考えていくと、人間の脳の特性を利用するのが良いという記事に出会った。
この特性という観点から考えると、現実的な打ち手は究極、2つだけになるという。それは以下の通りだ。
嫌いな人への関心を他に向ける
嫌いな人をどうでもいい人に変える
前者の関心を他に向けるとは、実は「没頭」のことを言っている。意識は1つのことにしか向けられないのだから、それを嫌いな相手や、有毒な思考に向けるのを止める。
そのためにリフレッシュと称して趣味に打ち込むことは、現実からの逃避でもなんでもなく、一旦冷静になって物事を観察するためにもマストな一手だ。
そして後者のどうでもよくするとは、「そんな人(≒残念な人)もいるよね」という程度の感想で終わりにすること。いわば、「なぜ」を深掘りしないことだ。
どうでもいい相手を理解する必要なんかない。残念な人だと思ったら、もうそれで終わりにすればいい。
そもそも、自分が思う理想の他者像というメガネを通して見るからこそ、そことの落差に不快感や忌ま忌ましさに包んだ怒りを覚えてしまうのだ。
例えば、「そんな人もいるよね」というのは、「夏だしセミも鳴くよね」というのとほぼ同じレベルにまで、相手の存在に関する意識を霧散させることと言える。
しかし、それがなかなか難しい。この記事を書いている今も、時折クレーマーに対して、頭の中に渦巻くものがないわけではない。
相手のことをなぜ許せないか。執着を手放せないのか。その問いのヒントとして、先のブログ記事には、こうも書かれていた。
①相手に嫉妬している
②相手と相性が合わない
③相手が嫌なことをする
①はちょっと無いとして、②と③はすごく納得する。相手が能動的に僕に対し腹が立つ言動を取っている。そういう事情があると、無関心であり続けるのもまた大変だ。
それについて、面白い思考法を授けてくれたのは、どこかサイコな考え方をきちんと言語化できている方々の話だ。
共通点として目立つのは、相手を自分と同じ常識や価値観・文化的水準を持つ人間という前提を捨てることだ。痛快で本当に面白い。
このことを、「動物」とか「別の生き物」あるいは「そういう役割のキャラクター」と割り切る人さえいる。ただ、言っていることは大体同じ。しれっと哀れむのだ。
中には、自分にムカつくことを言った人はもう死んでいると考えて、仮にまた姿を見ても、成仏できていない魂と思うだけとする例もあった。
なるほど、「死んだ」という言い方は過激ではあるが、自分が認知しなければ世界に存在しないも同じという意味で捉えるというこれ自体は、すごく腑に落ちる話だ。
そしてこれは、究極的な逆転の発想ではないだろうか。
仮に物理的に相手を殺したところで、逆にそれによって、憎い相手が未来永劫、四六時中、自分の心の中に生きることになってしまうかもしれない。
しかし認知を変えて意識から完全に消してしまえば、存在を知覚できないという意味で、つまり本当に殺すこと以上の平穏さが手に入るのではないか。
言っていることはなかなかに黒いと思うのだが、相手を殺したいという気持ちの目的は、恐らく相手の存在を跡形もなく消したいから、というのではないか。
そのことを考えると、やはりそれは認知を変えて初めて達成される話だと、どうしても思えてくる。
さて、少し極論に飛んだが、一旦まとめておこう。
「無関心」を使いこなすこととは、すなわち相手をどうでもいい存在に変えることであり、そのためにはまず没頭できるものに打ち込んで、精神的な距離を取る。
そのうえで相手に対する哀れみから入り、期待値をトコトン下げて、そして最終的に意識から完全に消し去っていくこと。
「無視」を超えた「無関心」という心の持ち方。鍛えれば鍛える程、平穏な人生が待っているように思えて仕方ない。
無関心≒他人事≒客観視≒やさしさ。

「無関心」を突き詰めれば、全てを他人事として解釈することであり、それは徹底した客観視をも意味する。
そう思うと、その思考の天性のプロが頭に浮かぶ。サイコパスだ。特に”良い”サイコパスの方々の考え方は、「無関心」の極地にあると思わされる。
ただ、修行の果てにそこへたどり着く人たちもいる。それが仏教僧だ。座禅を始めとする修業の果ては、徹底した客観視、いわば磨き上げられた観察力。
実際、仏教僧とサイコパスの頭の使い方は、CTスキャンでもそっくりだという話を読んだことがある。天性か後天的か、そここそ違えど、辿り着く果ては同じ。
ただ、その両者が醸し出す雰囲気は、表面上すごく似ている。それは懐の大きさだ。感情を乱さず、冷静に、ユーモアある対応や言動を常日頃から”できている”。
その根幹にある思考が、「全てを他人事として考える」ことであるならば、その余裕に寄与している時点で、他人事思考は、実はとても自分に優しい思考法ではないか。
確かに、他人に与えるアドバイスは、自分が自分に投げる言葉より、ずっと柔らかく優しく、そしてその人に寄り添っている。すごく納得だ。
どうでもいい相手にこそ、実は優しくできる。

それが真理だとすると、寂しい響きも無いことは無いが、「みんな違って、どうでもいい」が合言葉の世界は、確かに平和だとも思う。
実際、「見守る」と言えば愛のある言葉に聞こえるが、これの言わんとすることは、信じたうえでその人に一任することだ。つまり、”干渉しない”。
無関心も他人事も客観視も、行き着く先は”やさしさ”なのだとすれば、数千年も数多の悩める人達が修業を重ね続けてきた歴史の重みの意味が、僕の中で変わる。
それに、客観視を徹底することは、実は大切な自分自身という個性を守ることにも繋がる。その指摘は、これまた斎藤一人さんの言葉がわかり易い。
これまたソースが記憶の中となるため、あくまでも発言の雰囲気の紹介になるのだが、引用してみる。
自分にとって嫌な奴がいたら、無視して良いの。間違っても機嫌を取ったり、好かれようとしたりしなくていいんだよ。
もしあなたがその嫌な奴に好かれちゃったとしたら、類は友を呼ぶって言うじゃん、あなた自身が嫌な奴になっちゃったってことなんだよ。
自分のことを嫌う人に合わせた結果、自分が嫌われるって、バカバカしいよ。
・・・容認できないアホの心理を想像し、擦り寄って、もしその人と共感できてしまったら、自分にとって嫌な人間に、自分が近づいてしまったことの証左。
八方美人のリスクの極みが、飄々としたメッセージの中に、わかり易く端的に、一切オブラートに包むことなく込められている。
僕はそこにゾッとしたものを覚える。自分が嫌いな人には嫌われ続けておかないと、大事なものを見失うという危惧が、一層強くなったのを感じている。
慈悲は利他から生じる利己の感情。

この項の最後に、僕にとって意外な意味合いを持つことに気付いた言葉を紹介する。それは、先述もしているが、「慈悲」だ。
「慈悲」とだけ聞くと、無条件に他人に対して愛を注ぐことといった、利他の極みのような言葉にも聞こえる。
しかし仏教で説かれることを調べていくと、「慈悲」が本当に伝えたい点は、実は続きがあるのだと知った。
そしてそれを学んだとき、僕の中で、「他人事に思うのは冷たい」とか、「無関心は少し酷い」といった一片の迷いが、完全に消えたのだ。
そのきっかけとなった定義を、紹介する。
慈悲とは、”他人を慈しむように”、自分に優しい声掛けをすること。
―その優しさの最終目的地は、つまり自分なのだ。他者への慈しみを通じて愛を学び、その愛を最後は自分に注ぐ。
「無関心」によって距離を取り、主観を廃した助言を大事な人にかけてあげるように、それを自分にも施してあげる。
スルースキルとは、「慈悲」を自分のものにするために必要な、修行のプロセスを指す。ここまで書いて、僕の中では意味合いが、こんな風に更新されている。
終わりに:僕にとって、「気にしない」とはなにか。
「気にしない」とはなにか。それを起点に、何度も何度も自問自答する。その果てがこの記事である。
ここまで書き殴った今、僕はどんな答えに辿り着いているのか。
暫定解だが、書く。僕にとって「気にしない」とは、「気にする」対象を、周りの要因関係なく、主体的に決め続けることである。
例えば嫌なことがあったとき、そのことに意識を向けず、他の生産的で楽しいことにそれを向ける。また、必要に応じて、そもそも思考さえ止めてしまう。
緩急自在に自分の思考をコントロールして、自分にとって害となる人や思い出、価値観を徹底的に頭から締め出すこと。
受動的な考え方ではなく、むしろ逆で、積極的に攻めるような思考法が、「気にしない」の正体。今はそう納得している。
人生は有限だ。自分にとって嫌なものに意識を向ける時間は、ただの無駄だ。そして理解できないアホな論理に付き合うのは、人生そのものの浪費に他ならない。
僕のことが嫌い。だから何だ?そんなことを「気にする」くらいなら、今日の晩飯のメニューを考えていた方が、遥かに有意義で生産的である。
だから僕は、もっと楽しいこと、有意義なこと、大事なことを「気にする」。くだらないことはそうだと認識して、徹底的に「気にしない」。
どんだけこちらが働きかけようが、アホはアホだし、犬のウンコは道端に落ちているし、SNSにはアンチが沸くし、現実は不条理で、ろくでもない目に遭いまくる。
それらを解決するには、人生はあまりにも短い。でも、それらを「気にしない」ことは、きっとできる。
僕の人生にもあなたの人生にも、もっと「気にするべき」ものはたくさんある。
アホの側にいる自分の味方を見よう。犬のウンコの側に咲く綺麗な花を見よう。アンチではなくコンテンツを楽しもう。
「無視すんなー」とヤイヤイ騒ぐのは、無視されて然るべき残念な方々ばかりなのだ。その人達を「気にした」ところで、何が残る?
自分に対して敵意や悪意がある存在だけが周りに残る未来は、あまりにも惨憺たるものだ。想像さえしたくない。
第一歩は、繰り返しになるが、「気にする」対象を、周りの要因関係なく、主体的に決め続けることである。
嫌なことは考えない。究極、それでいいんだ。とても能天気な帰結に聞こえるが、ここには強い意志が存在しているんだと、今はよくわかっている。
さて、今日も、楽しいことや面白いことだけ考えよう。嫌なことや不安なことは頭から締め出そう。そのために自分ができることに意識を向けていこう。
僕の「気にしない」修業は、始まったばかりなのである。
2023年 9月某日 窓の外に輝く綺麗な夕日を見ながら
